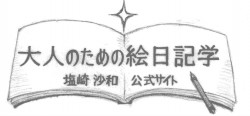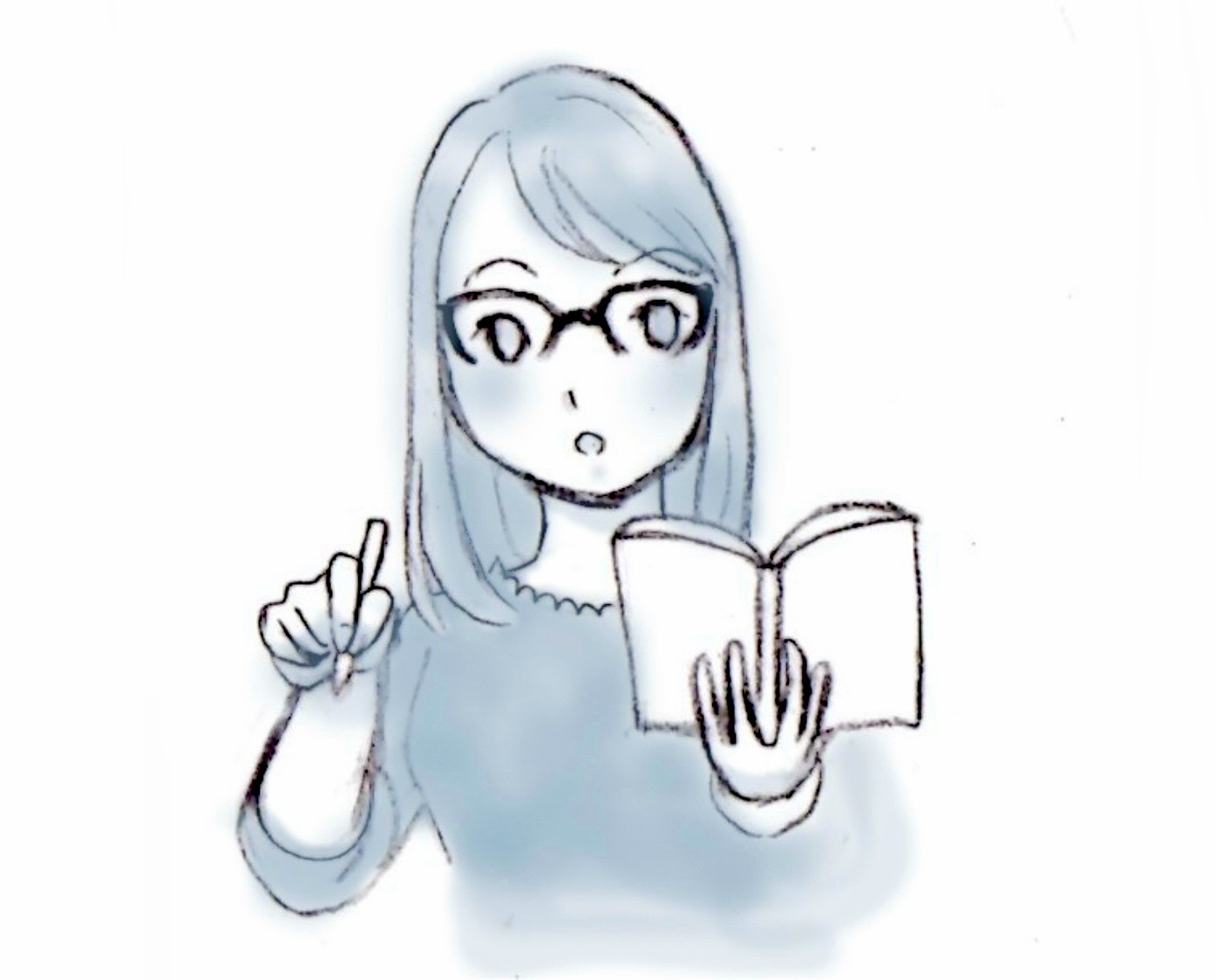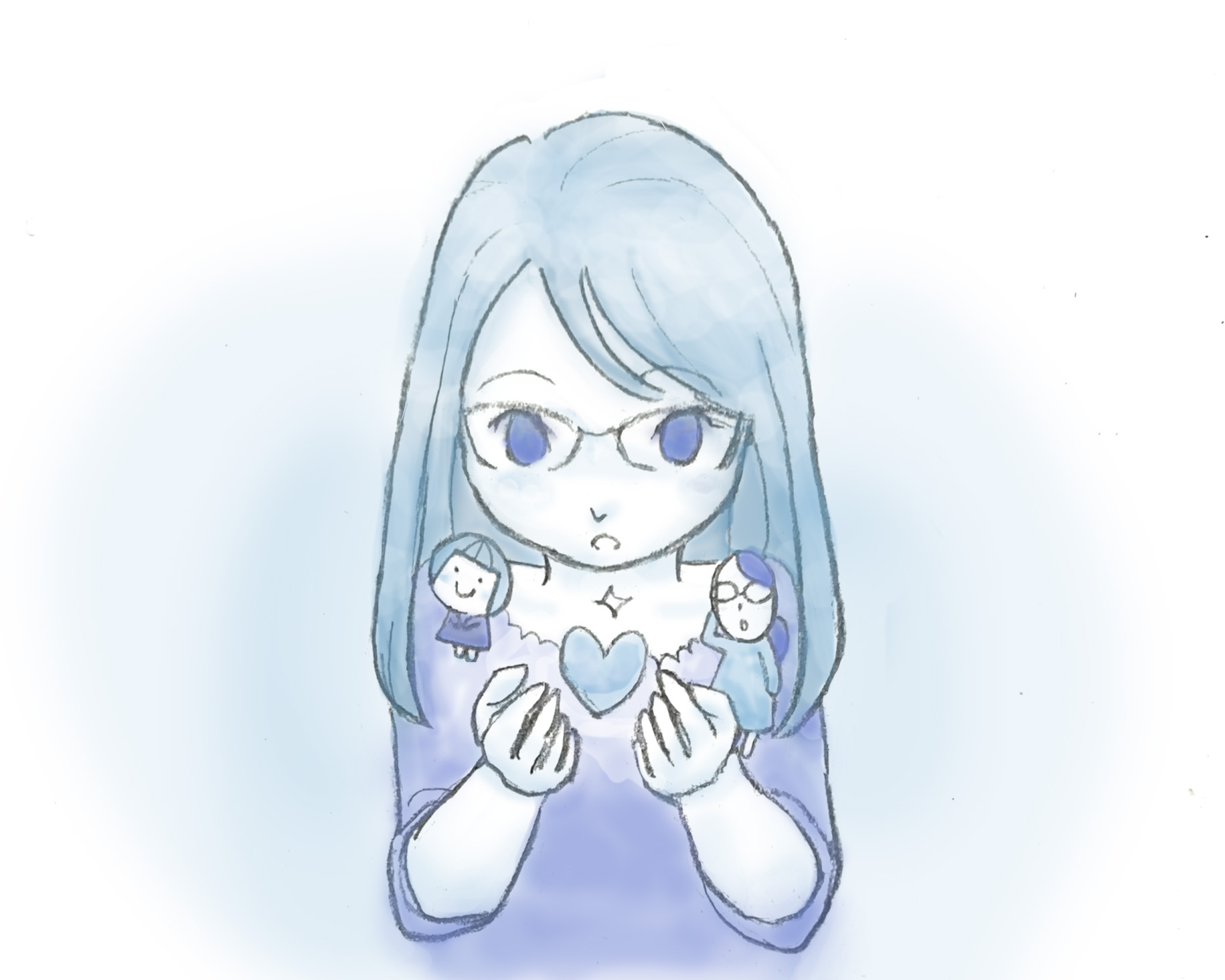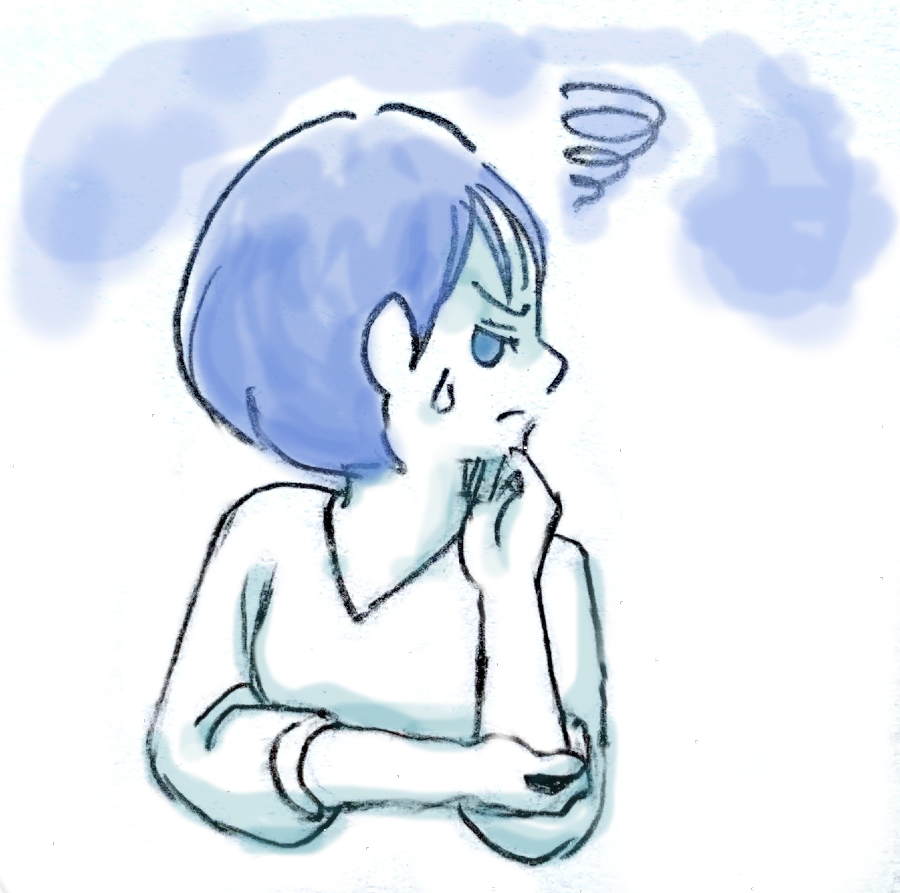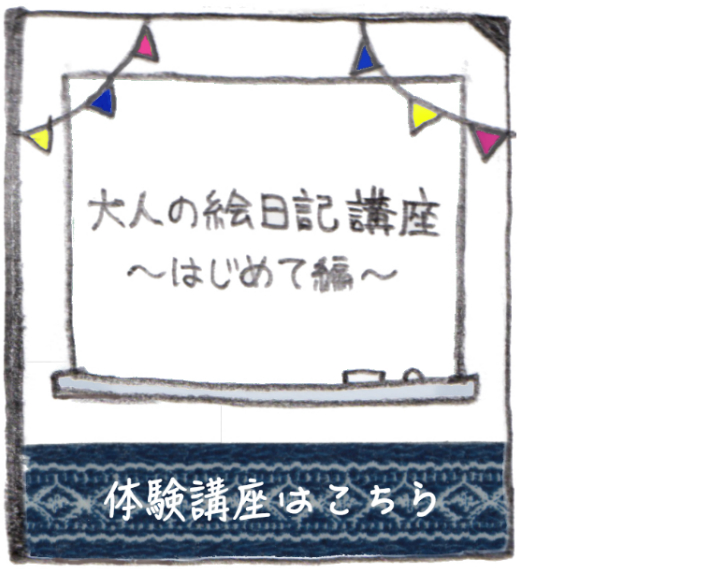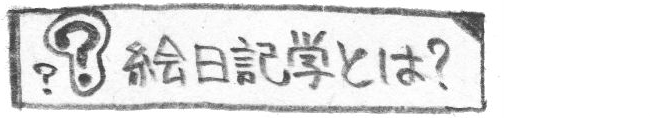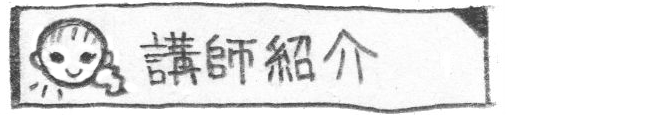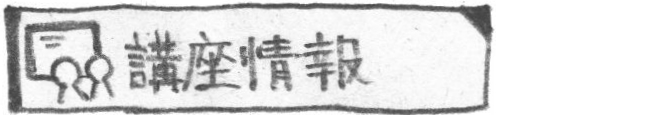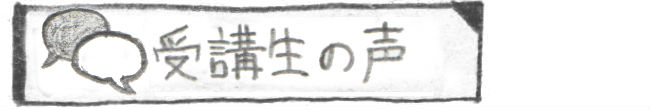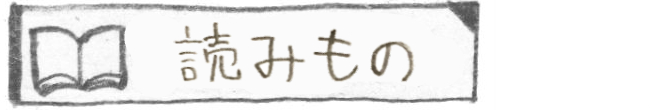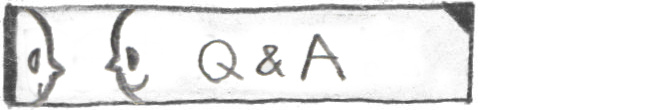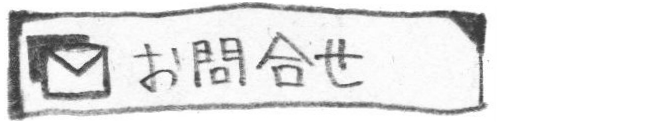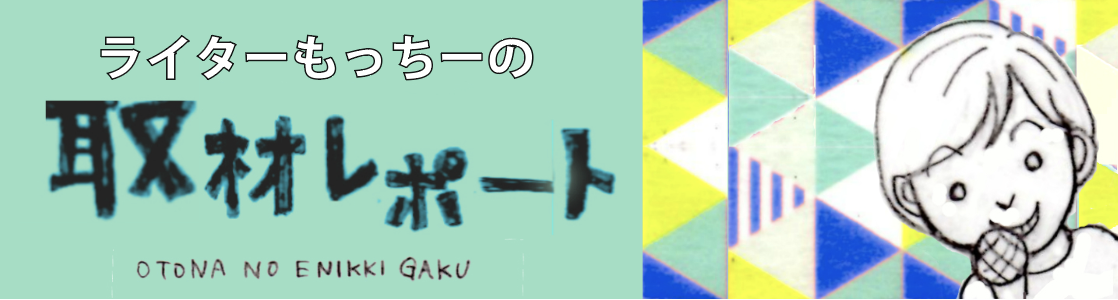外向型が感情を見失う理由と取り戻すための方法
明るく前向きで、行動力がある。
人から相談されることも多く、
自分はそこまで深刻に悩むことがない。
落ち込んでもすぐ頭を切り替えて、
「どうしたらうまくいくか?」
を考えて対処法や突破口を見つけてきた。
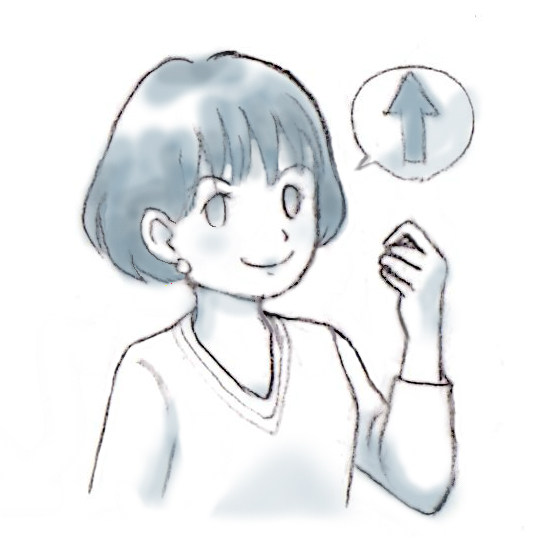
心理学では、
自分の“外”の世界に意識が向きやすく
新しいことや人との関わりなど
外部からの刺激を好む人のタイプを、
『外向型(extrovert)』と呼びます。
そんな元気な人が、ある時ふと
「自分の気持ちがわからない‥‥」
という壁に直面することがあります。
それは、今まで感情を無視してきたせい
ではありません。
むしろ、これまで
ポジティブさと努力で前進してきた
『外向型』の人だからこそ起きやすい
クライシスなんです。
今回は、
そんな外向型の人がぶつかりやすい
「心の空白」の正体と、
そこから抜け出すためのヒント
について書いてみたいと思います。
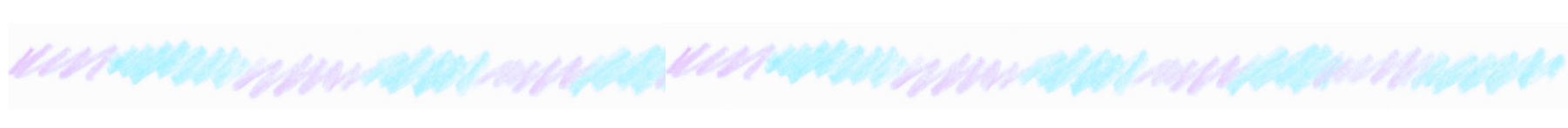
外の世界で前向きに生きる外向型
外向型の人には、こんな特徴があります。
- 自分の外の世界にある刺激や体験、人との交流が好き
- 嫌なことがあっても、楽しいことや前向きな思考で切り替えられる
- 行動力・向上心があり、基本的にポジティブ
そのため周囲から「明るく元気な人」として
好かれることも多いでしょう。
けれど大人になると、
「いい人だなとは思うんだけど、
あなたの気持ちがよくわからない」
と大切な人から言われることがあります。

「まあ、気にしててもしょうがないか!
また頑張っていこう!」
と、いつものように
前向きに切り替えられるはずが、
「‥‥あれ?本当の気持ちってなんだっけ?
自分の中が空っぽな気がしてきた‥‥」
今まで順調だった外の世界での活動から、
突然内側の空洞感に直面したりします。
特に、本来は感受性豊かだった人が
思考的な大人として頑張ってきた場合、
なぜかいつものように軽く流せず、
この感覚に強い焦りを感じます。
「どうすればいいだろう?」
とすぐ対処法を探し始めると
また意識が外に向かってしまい、
内側にある気持ちから遠のいていきます。
(方法もちゃんと後述するのでご安心を!)
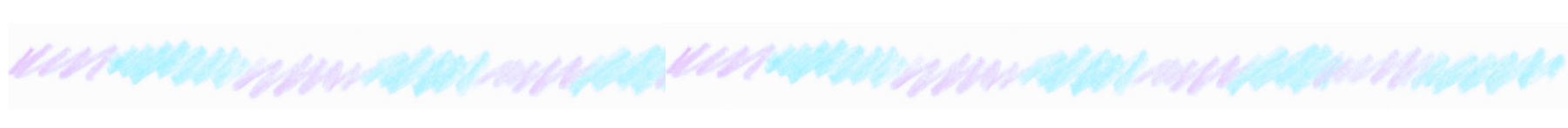
感情がわからなくなる理由
外向型の人はもともと内省が苦手で、
感情よりも「思考」や「行動」に
意識が向きやすいところがあります。
気持ちを切り替えるのが早く、
対処力もある。
「楽しい、好きってちゃんと感じるし、
自分の気持ちはわかってるはず」
と思うかもしれません。
でも、その自覚している感情を見つめると、
“ポジティブな感情”と”ネガティブな感情”で
感じ方に偏りがあることに気付きます。
不安、悲しみ、怒り、嫌悪、無力感
といったネガティブな感情は、ある
‥‥けど、なんか薄い。。
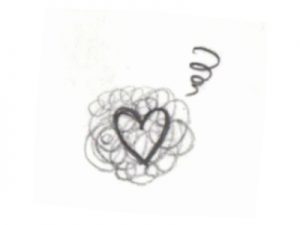
つまり外向型は、
ネガティブな感情をじっくり感じる前に
「行動」で処理するのがうまい人なんです。
それが強みである一方で、
「無意識に感情をスルーする癖」を
育ててしまうことでもあります。
その結果、ある日突然
心の壁にぶつかることがあるのです。
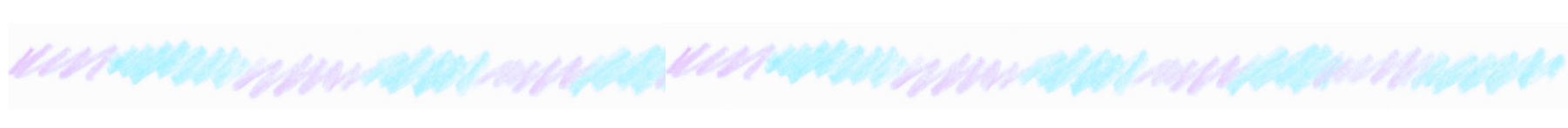
空白感と向き合えないのはなぜ?
「でも、わざわざ嫌な気持ちを
感じなくてよくない?」
という疑問もわかります。
つらい感情をわざわざ掘り返すなんて。
それにこれまでも、傷つかずに前を向いて
うまくやってこれた。
でも、だからこそ今、
その方法では限界がきて壁にぶつかっている
とも言えます。
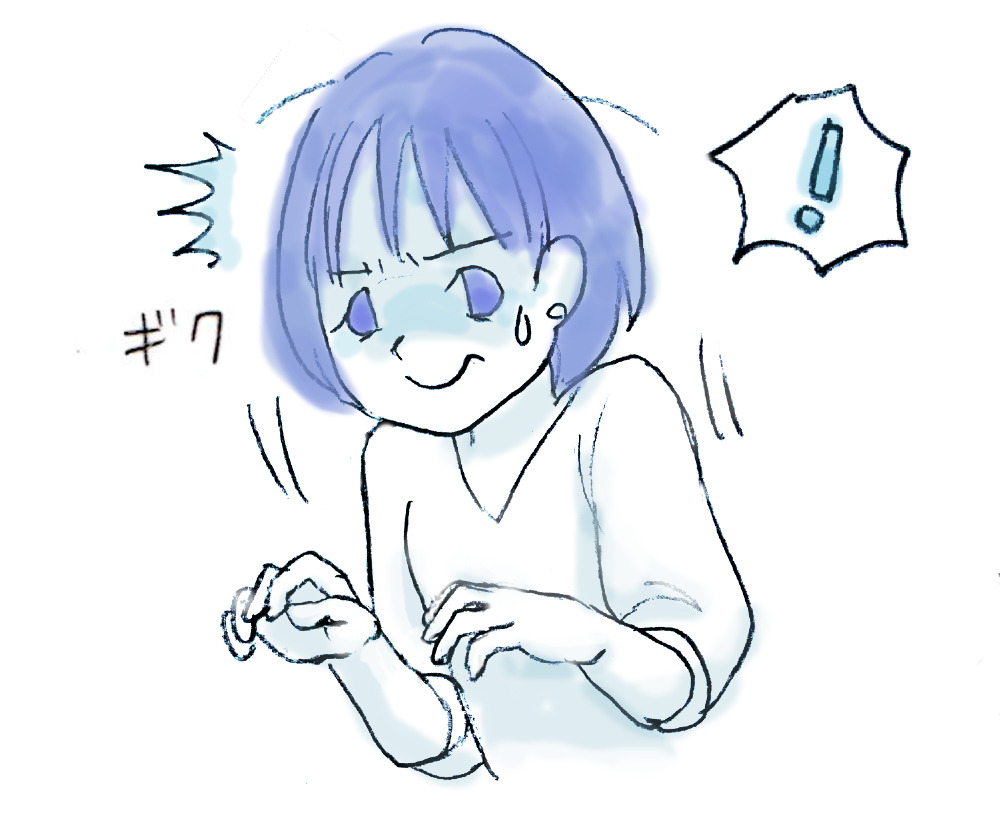
しんどいのに理由がわからない。
達成してもどこか満たされない。
自己分析をしても「知識」にしかならない。
それは、ずっと避けてきた
自分の「本当の気持ち」に
まだ出会えていないから。
考えても表層的な気持ちより先に深掘れず、
そのまま思考と行動の堂々巡りに
陥ってしまうのです。
でも、それも無理はありません。
もともと外向型は、ネガティブな感情や
弱さと向き合うのが苦手。
だからこそ、外向型の人が
自分一人の力でそこに向き合うのは
とても難しいのです。
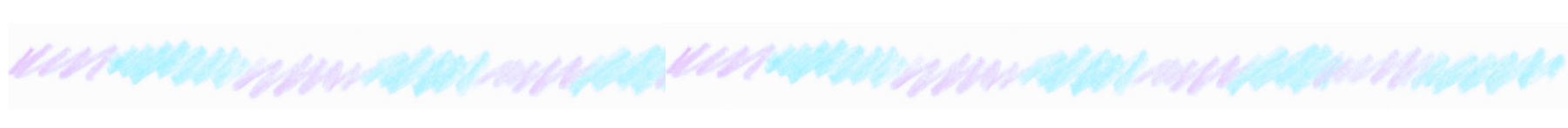
感情に向き合うツール
「‥‥で、どうすればいいの?」
とすぐに方法を聞きたくなるのも、
外向型あるあるかもしれませんね。笑
「自分の気持ちがわからない」と感じた時、
意外な解決方法になるのが『絵日記』です。

外向型の人は、
目の前の出来事にすばやく対応する分、
その時に自分が「何を感じていたのか」を
後から思い出しにくいところがあります。
感情よりも行動や思考が先に出てしまい、
すぐ次のことに意識が向くからです。
だから、内省をしようと
いきなり今の感情を見つめても、
よくわからないまま終わってしまいます。
そこで、日記で日々を振り返ってみると、
「出来事」という
具体的な感情のキッカケがあるため、
「あの時本当はこう感じていたのかも」
という気付きが生まれやすくなります。

さらに、絵を描くことで、
うまく言葉にならない感覚や感情を
言葉にせずに表現できるようになります。
外向型にとって、絵は
「感じながら考える」ための貴重なツール。
言葉だけの「日記」だと
思考ばかりを書いてしまうタイプでも、
非言語である絵が入ることで、
感情や感覚を自然に出せるようになります。
(絵が苦手でもちゃんと効果があるのも、
絵日記学のいいところです)
絵日記学では
感じる→書く・描く→読み返す
というプロセスを通して、
少しずつ自分の「本当の気持ち」に
出会えるように設計されています。
日記は繰り返すものだからこそ、
自分自身の感じる力も育っていくのです。
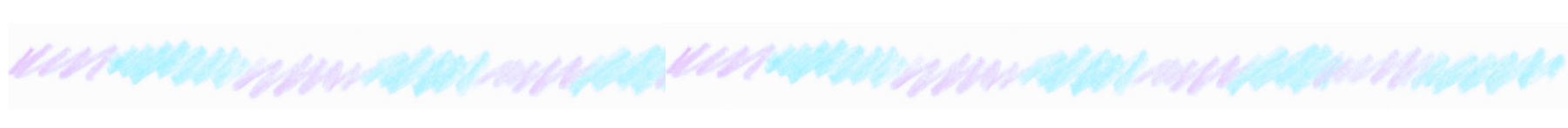
なぜ外向型でも変化できたのか
‥‥とはいえ、持ち前の好奇心で
「なんか面白そう!」で始めてみたものの、
- 感情が書けない
- 地道にコツコツできない
- 書いたけど思考&ポジティブなことばかり
と外向型の壁にぶつかることがあります。

「じゃあやっぱり外向型に絵日記は
向いてないのでは?」
と思うかもしれませんが、
実際には、外向型でも
そこから大きく飛躍した生徒さんが
何人もいます。
そこを越えられた人が持っていたのは、
「絵日記を書く意味」です。
思考が強めの外向型の人にとって、
ただ感情を感じるだけでは
動機づけになりません。
「自分がなぜこれを書くのか?」を
頭でも理解し納得しているからこそ
挫折しにくくなるのです。
絵日記学の講座が、進めば進むほど、
この「書く意味」が確信になっていきます。
最初は少しずつでも、
絵日記に書いたいろんな自分の気持ちを
自分自身がわかってあげることを
積み重ねていく行為。
この、一見効率の悪そうなプロセスは、
「自分の本当の気持ちがわからない」
と感じていた空白の心に、
「自己信頼」の気持ちを育てていく
ことにもつながります。
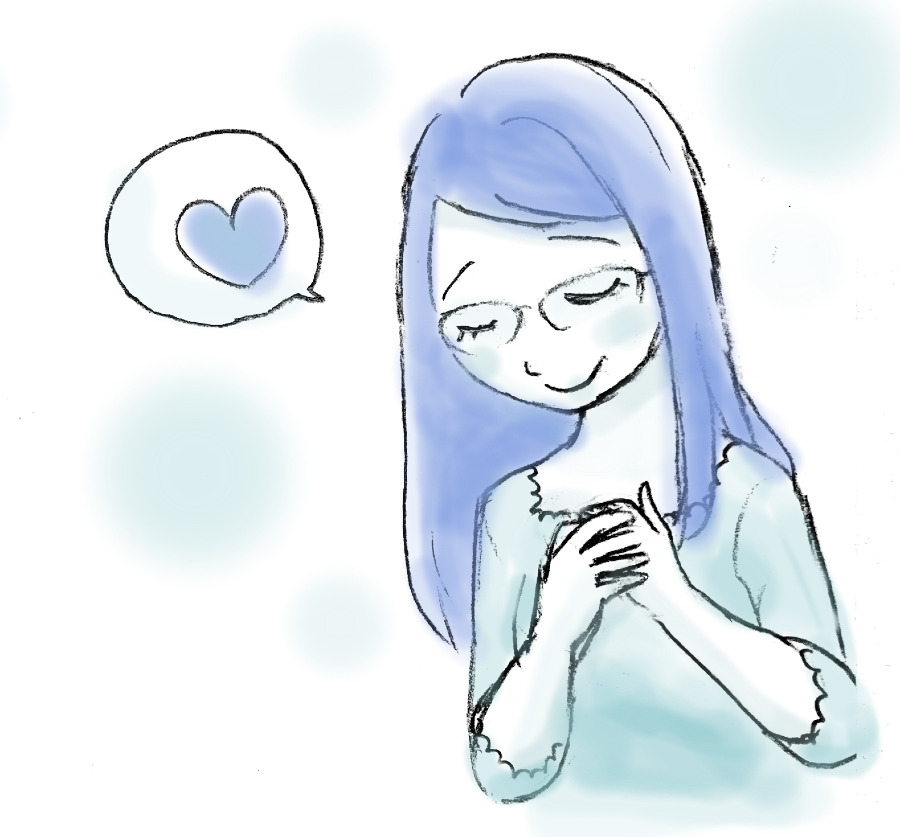
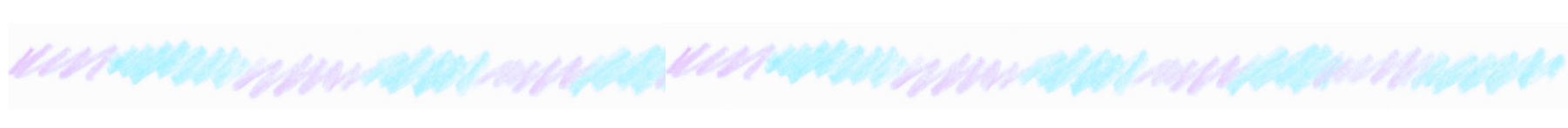
外への力と内からの力
外向型は内省が苦手だから
自分と向き合う絵日記学は非効率。
でも、実はその逆かもしれません。
内省が苦手だった外交型の人が
自分の内面と向き合えるようになった時、
本当の意味で“心のバランス”を取り戻し、
「外に向かう力」と「内なる深さ」の
両方を手に入れるからです。
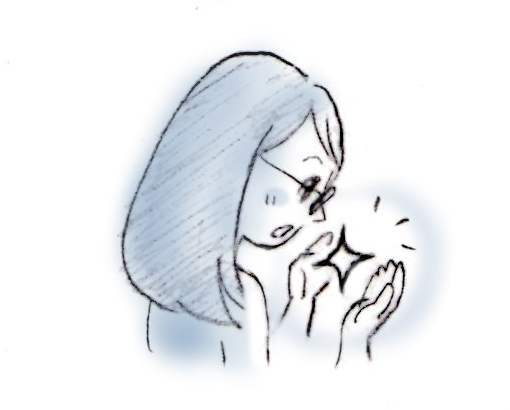
「自分の本当の気持ちがわからない」
という課題に正面から向き合い、
それでも自分の気持ちを見よう
と試行錯誤した人は、
当然、人としても成長します。
わからなさに戸惑いながらも
それと向き合おうとした経験こそが、
外向型の人の内面を育て、
「自分」を持った芯のある大人に
してくれるのだと思います。
|
▼関連記事 |

外向型でも自分の気持ちを見つけてみたい
と感じた方はこちら