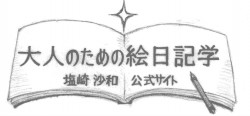真面目に自己肯定感のワークをしても効かないのは、内向型のせい?
「落ち着いて見える」と言われるけど、
頭の中はずっとぐるぐると
いろんなことを考えてて言葉だらけ。
人混みや集団行動は苦手で、
静かな場所や一人の時間がほっとする。
感情は感じてるけど
言葉に出せなかったり、
自分の気持ちが抱えきれず
どうしたいのかわからなくなる時がある。
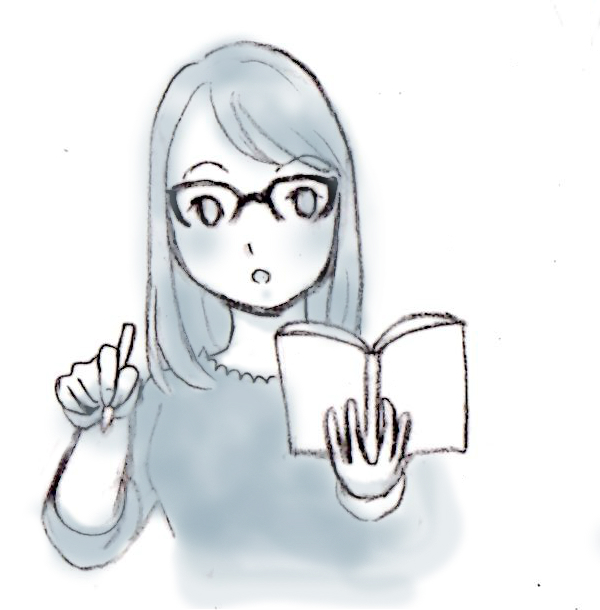
心理学では、
自分の内面や感覚に意識が向きやすく
一人の時間や静かな環境を好む人のタイプを
『内向型(introvert)』と呼びます。
内向型の人は、外からの刺激よりも、
自分の感じたことや考えたことを
じっくり味わうタイプ。
表には出さなくても、
コツコツと見えない努力を重ねたり、
深い集中力や豊かな共感力、
ユニークな創造力を持っていたりします。
そんな内面の豊かな内向型の人が、
大人になるにつれて
その“内面”でつまづくことがあります。
たとえば、自己肯定感を上げようと
本を読んだり、ワークを頑張ったのに、
なんだかどれもうまくいかなくて、
余計モヤモヤ苦しくなる‥‥
それだけなら
わりとあることかもしれませんが、
内向型の人はそのモヤモヤを外には出さず
自分の中に溜め込みやすいため、
自覚している以上に蓄積されている
ことが多いのです。
すると自分の気持ちの感じ方にも
影響が出ていきます。

これは、もともと感受性が豊かで
自分の内面の問題に向き合おうと
真面目に努力してきた人ほど起きやすい、
内向型特有の“静かなクライシス”なんです。
というわけで今回は、
「感情は感じてるはずだけど、
なんだかずっと晴れずに疲れる‥‥」
そんな内向型の人の、
自分の気持ちをどう扱えばいいか?
についてお伝えします。
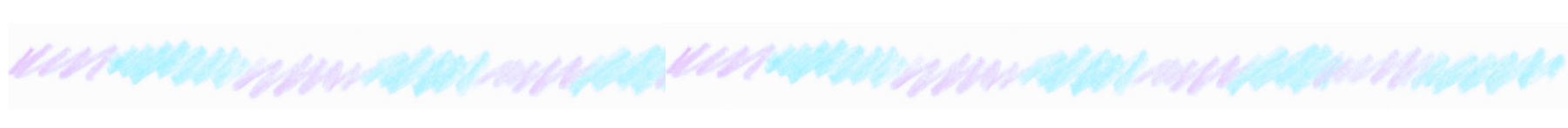
内向型が陥る感情の迷子
「感情は感じてる‥‥けど、
この気持ちが本当なのか自信がなく
うまく言葉にできない」
「前向きになろうと努力するほど、
どこかで“本当の自分”から
ズレていくような感覚がする」
「心の勉強やポジティブな思考法を試しても
なんだかモヤモヤしてきて、
自己肯定感が全然上がらない」
「子どもの頃は自然に感じていた気持ちも、
大人になると考えることばかりで
気持ちを抑えることが癖になってしまった」

そうして自分の気持ちだけでなく、
自分自身そのものにも
だんだん自信がなくなっていきます。
感受性の豊かさと真面目さゆえに起こる、
内向型ならではのつまずきです。
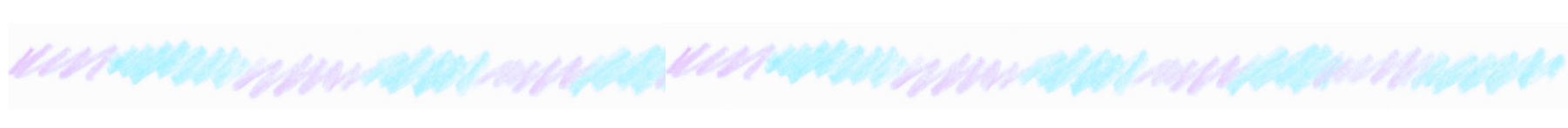
頭の中でぐるぐる思考するしくみ
なぜ本来は感受性が豊かな内向型の人が、
「気持ちがわからない」
「自信が持てない」
という状態になってしまうのでしょうか?
その背景には、
内向型ならではの“考え方の癖”と、
大人になるにつれて身につけた
“心の習慣”があります。
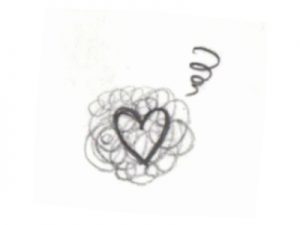
①外の基準に合わせる気づかいスキル
人に合わせるのが上手な内向型の人は、
社会で求められる
「考えて行動するスキル」を身につけます。
ただ、それが仕事以外でも定着し、
感情を抑え思考で動こうとします。
②感覚の抑制と言語化の難しさ
感覚や気持ちを表現する機会が少ないと
考えることばかりが強化されてしまい、
自分の感じたことを
うまく言葉にできなくなっていきます。
③ネガティブ感情との同一化
感情を深く丁寧に感じるタイプだからこそ、
ネガティブな感情を味わいすぎて、
ほんの一時的な気持ちも
「自分の性格」と結びつけやすくなります。
なのに、ポジティブな感情は
「勘違いかも」「たまたまだろう」
とスルーするため、
ネガティブな感情だけが「自分」として
残ってしまうのです。
④思考の暴走
感情が感じられなくなると、
自分の中で思考が暴走し
抜け出せないループにはまります。
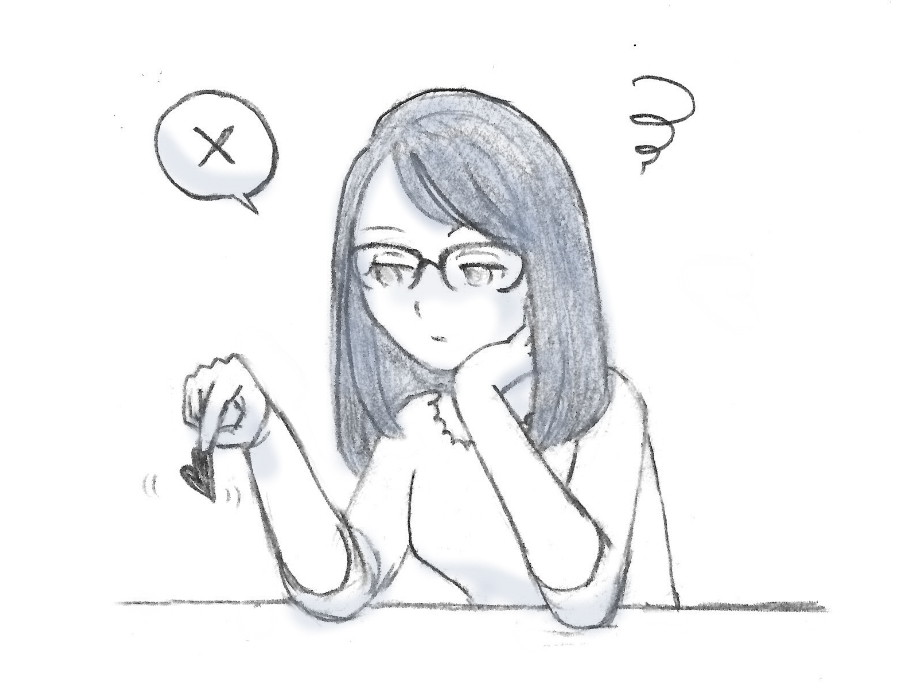
このような思考と感情の偏りが、
内向型の人が「自分の気持ちがわからない」
と感じる原因になっていくのです。
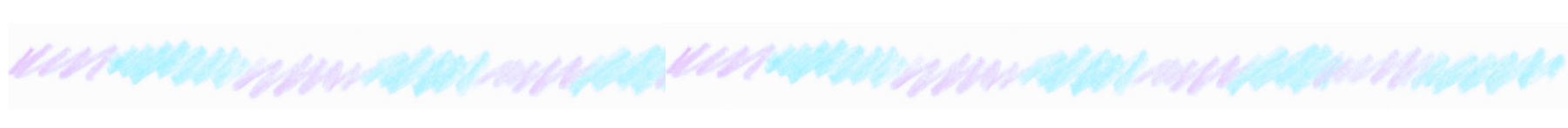
内向型の努力は報われないのか
それでも真面目な内向型の人は、
どうにかしようと一人で努力を重ねます。
でも、
- 頭ではわかってるけど変われない
- ポジティブになろうとするほど、
逆に苦しくなる - いくら本を読んでも腑に落ちない
- 自己肯定感のワークが白々しく感じる
- 心がついていけずモヤモヤする
感受性の強さも相まって、
自分の中に感じた違和感が
重くなっていきます。
「他の人はこれで変われたのに、
なんで私だけ効果ないの?
やっぱり私には無理なのかな‥‥」

そんなふうに
またつい自分を責めようとしてしまう
かもしれませんが、
それでも一生このままは嫌だと感じ、
どうにかしようと自分を諦めずにきた証拠
でもあるんです。
内向型の人は、とても思考が深く、
繊細に物事を考えられます。
でも、その「思考」だけで取り組むと、
また「感情」が置き去りになってしまい、
自分を信じられなくなるのです。
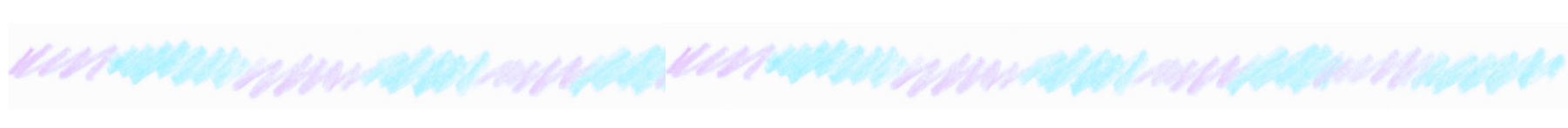
方法論より、感じる力を取り戻す
「でも今まで感情のことも色々勉強しても
ダメだったんだけどなー‥‥」

そうして、またどうせダメかもと
慎重になるのもまた内向型の特徴です。
(でも今のまま一生も嫌だからと、
一応試してみるところも)
大切なのは「考え方」や「やり方」ではなく
「感じる力を取り戻すこと」です。
感じる力は、
内向型の人が本来持っていた力です。
でも、思考が優位になりすぎると、
その感情や感覚を
自分でうまく扱えなくなってしまいます。
でも、感じる力を取り戻すって、
どうしたらいいのでしょうか?
そのヒントになるのが、『絵日記』という
ちょっとユニークな方法です。

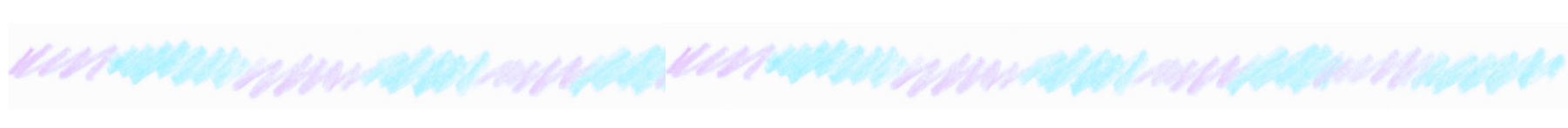
安全な「気持ちの出口」を作る
内向型の人は、
自分の中では色々感じていても
それを出す時に
心でブレーキがかかることがあります。
うまく言葉が出てこなかったり、
「感じたけど違うかも‥‥」
と迷い、抱え込んでしまう。
絵日記は、そんな内向型の人にとっての
感情を安心して出せる場所になるんです。

絵日記なので、
誰かに見せるものではありません。
だから、うまくまとめる必要も、
正しさもいりません。
自分のペースで、
自分の感じたことを
そのまま出すためのもの。
「出すのは怖いけど、
出さずに抱えるのも苦しい‥‥」
絵日記は、そんな心が板挟みの時の
ちょうどいい中間地点なんです。
さらに、
言葉にしなくても表現できる
のが「絵」の強み。
内向型の人は、言葉を使うと
つい思考モードになりがちですが、
非言語の絵なら
自分の本音が出てきやすくなるのです。
うまく描けなくても大丈夫。
ただ線や色を描くだけでも、
自分の内面を外に出せたことで
心が少しずつ変化し始めます。
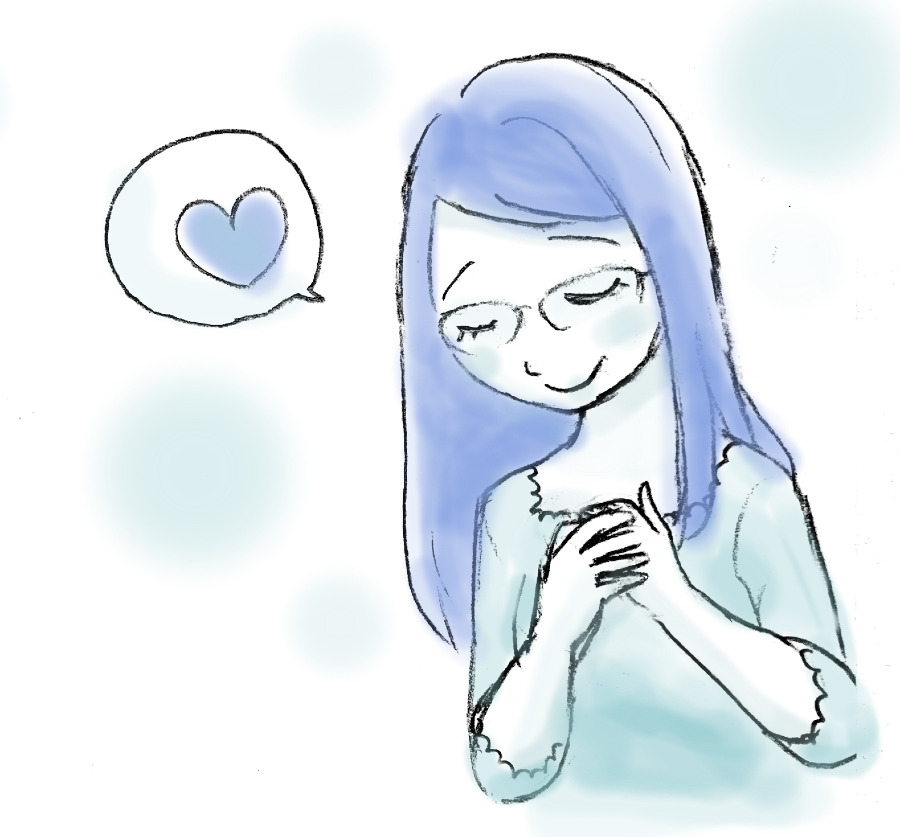
描いている時は気付かなくても、
後から見返して
「あぁ、あの時
私、こんな気持ちだったんだ」
とわかる。
自分の内面と後からゆっくり対話できる、
絵日記ならではの効果です。
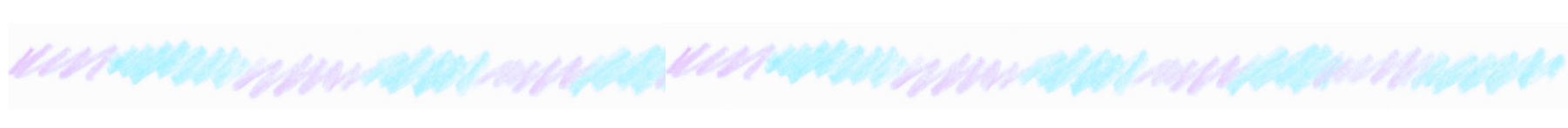
外への力と内からの力
内向型の人は
自分の中でじっくり考えすぎて、
感情を外に出すのが難しくなったり
否定的な思考に偏ってしまう
ことがあります。
でも、講座の中で内向型の生徒さんが
絵日記を書き続けるうちに、
その人の中にしまわれていた
豊かな世界を表現し始めていく
という変化をよく目にします。
最初は絵日記の中に、
よくわからなかったり否定的な感情を
ただ吐き出して終わりかもしれません。
それでも続けていくうちに、
そこに深い考えやユニークな発想、
好きなことややってみたいことなど、
ポジティブな気持ちも
少しずつ描かれていきます。
(内向型の生徒さんの書く絵日記は、
この内面の変化が絵日記に反映されるので
面白いんですよね)
さらに講座の後半になると、
絵日記の中で整理された考えや気持ちが
外の世界でも表現される
ように変化していくんです。
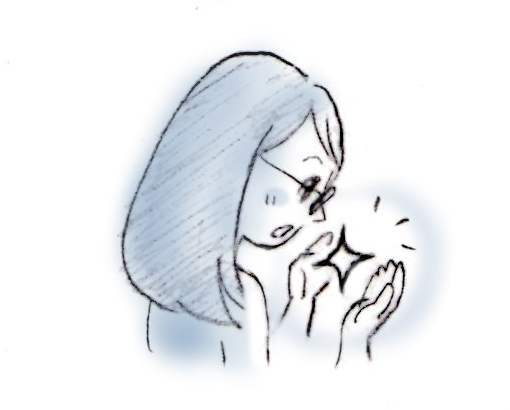
内向型の人は、本当はもうずっと前から
自分の中の世界を大事に育ててきた人。
だからこそ、内向型の人は
考える力と感じる力を
ほんの少しつなぎ直すだけで、
自分の中に軸が育ち、
「自分」を持った芯のある大人へと
変容していけるのだと思います。
|
▼関連記事 |

内向型の自分の気持ちを取り戻したい
と感じた方はこちら